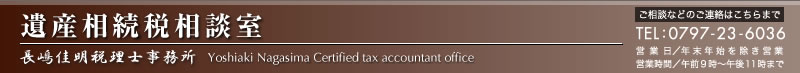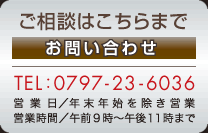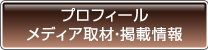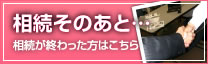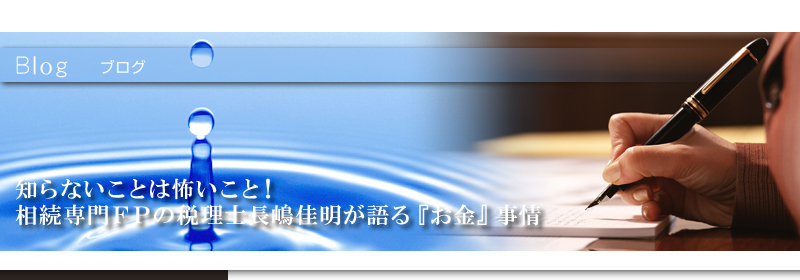
【遺産相続税相談】相続人が認知症のときは成年後見人が必要です
- 2009/07/18
先日、兵庫県の方より、遺産相続のご相談がありました。
相続手続きについて、何をすればよいのかわからないとのことでした。
お話をお聞きすると、相続人の中に認知症の方がおられました。
認知症の方がおられますと、遺産相続のお話が進められないので、成年後見人を付ける必要があります。
成年後見人についてのご説明のため、先日の土曜日に、いつもお世話になっている行政書士と一緒に、相続人の方のご自宅に訪問してきました。
【成年後見人は判断能力が十分ではない方の代理人です】
認知症や知的障害そして精神障害など、判断能力が十分ではない方は、預貯金や不動産などの管理をすることが難しいと思います。
また、遺産分割の協議をすることも難しいと思います。
このように、判断能力が十分でない方を保護するために「成年後見制度」というものがあります。
この制度を利用することにより、成年後見人となった方が、判断能力が十分ではない方の代理人として、遺産分割の協議に参加します。
つまり、成年後見人を付けないと、遺産相続の手続きが終わりません。
【成年後見人の手続き】
成年後見人を付けるためには、判断能力が十分ではない方が、本当に判断能力が十分ではないことを証明しなければなりません。
このとき、医師の診断書が必要となります。
次に、家庭裁判所へ申し立てをして、家庭裁判所が成年後見人を選びます。
【成年後見人が決まらないと遺産相続の手続きが終わらない】
成年後見人が、遺産分割の協議に参加しますので、成年後見人が選ばれるまでは、遺産相続の手続きが進みません。
既に銀行口座が凍結されていますので、葬儀や法要の費用は、一旦相続人の方が立替えをしなければなりません。
葬儀の費用だけでも、一般的には300万円程度はかかりますので、他の相続人の方の負担が大きくなります。
このようなことから、事前に成年後見人の手続きをしていれば、他の相続人の方のご負担も軽くなったのではと思います。
【長嶋さんにお願いをしてよかった】
ご相談者様は、会社員の方ですので、週末しか動くことができません。
しかしながら、家庭裁判所は平日しか開いておりません。
また、家庭裁判所へ成年後見人の申し立てをするのに、必要な書類を準備しなければなりません。
成年後見人を選ぶことから今後の遺産相続の手続きが終わるまで、一連の流れをご説明させていただいたところ、「素人の私たち(ご相談者様)では、とてもではないが対応することはできないと思います、長嶋さんにお願いをしてよかった」と嬉しいお言葉をいただきました。
家庭裁判所へ成年後見人を選ぶことについての申し立てをすると、2ヶ月程度は時間が必要です。
それからの遺産相続の手続きですので、今年中にすべての手続きが終わるかどうかという状況です。
一日も早く、ご相談者様の肩の荷が下りるように、長嶋も祈っています。